Pythonエンジニア必見!アプリ開発とWeb開発の基礎を学べるおすすめ本7選
"AIエージェント開発とRAG技術を体系的に学べる実践的な入門書。LLMアプリケーション開発の基礎から、OpenAI API、プロンプトエンジニアリング、LangChain、そしてLangGraphを用いたAIエージェントの実践的な開発方法まで、豊富なコード例と共に解説。最新のAI技術動向に対応し、AIを使ったプロダクト開発に挑戦したいエンジニアにとって、キャッチアップと応用力習得に最適な一冊です。"
![LangChainとLangGraphによるRAG・AIエージェント[実践]入門 (エンジニア選書)の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51F6VKoZGSL._SX342_SY445_ML2_.jpg)
西見 公宏, 吉田 真吾, 大嶋 勇樹
出版日: 2024/11/9
出版社: 技術評論社
ページ数: 496ページ
最終更新: 2025年7月17日
人気スコア: 195
大規模言語モデル(LLM)を活用したRAG(検索拡張生成)アプリケーションとAIエージェントシステム開発の実践知識を基礎から習得できる書籍です。OpenAI API、プロンプトエンジニアリングの基礎解説に加え、LangChainを用いたRAGの実践手法や評価、さらにLangGraphを活用したAIエージェント開発とデザインパターンまで網羅しています。特に、LangChain Expression Language(LCEL)の徹底解説や、LangSmithとRagasを用いたRAGアプリケーションの評価、AIエージェントのデザインパターンとハンズオンは本書ならではの強みです。LLMの性質を活かしたサービスや業務システムを構築したい方、RAGやAIエージェント開発の本格的な知識を身につけたい方におすすめです。業界地図を把握し、生成AIシステム開発の最前線で活躍するための実践的なスキルを効率的に学べます。
"AIプロダクト開発に挑戦したいエンジニアにとって、応用力習得に最適"
"LangChainの活用に限界を感じていたが、RAGやAIエージェント開発の可能性を実感"
"AIエージェント開発に挑戦したい方にとって間違いなく学びの多い良書"
対象レベル: AIエージェント開発に挑戦したいエンジニア
こんな目標を持つ人に:
※ この情報は5件の技術記事からAIが分析・生成したものです。 実際の内容は書籍でご確認ください。
"AIエージェント開発とRAG技術を体系的に学べる実践的な入門書。LLMアプリケーション開発の基礎から、OpenAI API、プロンプトエンジニアリング、LangChain、そしてLangGraphを用いたAIエージェントの実践的な開発方法まで、豊富なコード例と共に解説。最新のAI技術動向に対応し、AIを使ったプロダクト開発に挑戦したいエンジニアにとって、キャッチアップと応用力習得に最適な一冊です。"
"LangChainとLangGraphを活用したRAG(Retrieval-Augmented Generation)やAIエージェント構築のノウハウが凝縮されている。LangChainの基礎からRAG構築までを幅広く解説しており、本書を理解すれば簡単なエージェントを自ら構築できるようになる。AIを活用したアプリケーション開発のスキルを習得したいエンジニアにとって、実践的な手引きとなる一冊。"
"本書はLangChainとLangGraphの基礎から応用までをハンズオン形式で解説しており、AIエージェント開発の全体像を深く理解できます。特に、LangGraphの明示的なステート管理や条件分岐・ループ処理の実装方法が具体的に学べる点が強みです。読む前はLangChainの活用に限界を感じていましたが、本書を読むことでRAGやAIエージェント開発の可能性を実感でき、実践的なアプリケーション開発に自信がつきました。AIエージェント開発を学びたいエンジニアに強く推奨します。"
"LangChainやLangGraphの基礎からハンズオン形式の実装までを深く解説しており、AIエージェント開発の基礎を体系的に理解できる実践的な一冊です。特に、従来のLangChainでは難しかった条件分岐やループ処理をLangGraphで容易に実装できる点は、開発効率を劇的に向上させます。LangChain・LangGraphを用いたアプリケーション開発を学びたい方、AIエージェント開発に挑戦したい方にとって、間違いなく学びの多い良書です。RAGの実行パターンやステート管理についても詳細に解説されています。"
"この本は、厚さゆえに手に取るのをためらっていた分厚い技術書を、裁断と章ごとの製本という物理的な工夫で克服し、学習意欲を高める実践的なアプローチを提案します。これにより、気楽に読み進められるようになり、小さな達成感を得ながら学習を進めることが可能になります。初心者でも「これなら読めるかも」という気持ちになれる、分厚い技術書への新しい向き合い方を提示してくれる点が強みです。読書へのハードルが下がり、学びの楽しさを再発見できるでしょう。"
「LangChainとLangGraphによるRAG・AIエージェント[実践]入門 (エンジニア選書)」と一緒に紹介されることが多い本

Dustin Boswell, Trevor Foucher, 須藤 功平, 角 征典
130件の記事
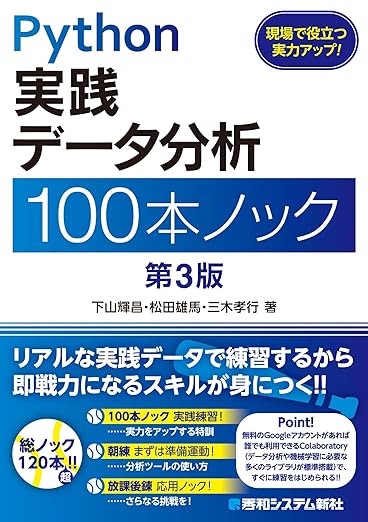
下山輝昌, 松田雄馬, 三木孝行
3件の記事
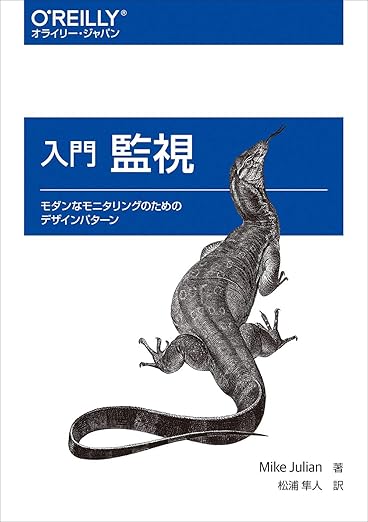
Mike Julian, 松浦 隼人
13件の記事
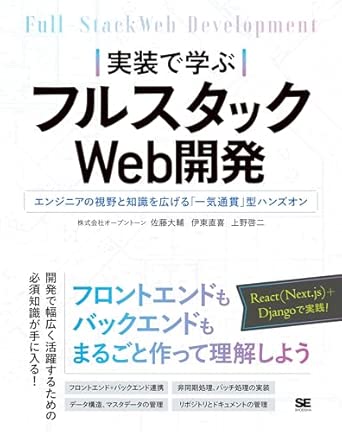
株式会社オープントーン, 佐藤 大輔, 伊東 直喜, 上野 啓二
2件の記事
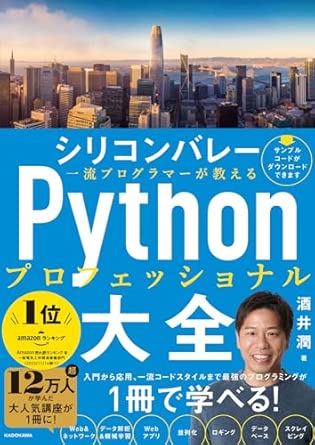
酒井 潤
3件の記事